立花さんとの対談について
今週の火曜日の立花さんとの対談は完敗でした。多少は期待してみていただいた視聴者の皆さんには本当に申し訳ないです。
完敗・・・負けたとはどういう意味か?
公開の対談において、相手をやり込めるという意味での勝ち負けなんてありません。
どっちが勝ったか負けたかではなく、自分の考えを視聴者にちゃんと伝えることができるか、そういう勝負で僕は負けました。立花さんは自分の考えを伝えられたが、僕はできなかった。
もっかいやれば、なんとかならないか、あのあと色々考えてみましたが、僕には無理ですね。やっぱり僕は文章を書く方が向いています。
立花さんも対談の感想を動画であげているようですので、ぼくは文章で対談の感想を書こうと思います。
わたしの対談でいいたかったことは事前にもツイートしたようにシンプルで、ガーシー議員のおこなった脅迫行為には、立花さんにも責任がある。という一点です。
立花さんは党首であるだけでなく、実際に脅迫行為に積極的に加担していました。脅迫した相手への攻撃は立花さん自身もおこなっていましたし、三木谷氏については暴露するターゲットにすることを指示したことについても対談中に認めています。
だいたい、立花さんすらも川上さんの件ではガーシーは言い訳できないと認める被害者であるぼくですら、立花さんに攻撃されてます。最後、土下座されてましたが、やるなら昨年の8月にやってほしかったです。
立花さんは暴露のなにが悪いんだと問題をすりかえていましたが、暴露が悪いのではなく、暴露するぞという予告によって脅迫していることが悪いのです。
暴露するなら予告せずにさっさと暴露すればいいのです。週刊誌だってそうしています。週刊誌は暴露の記事は書いても、暴露の予告の記事なんか書きません。まして予告だけを毎週連載なんてことはしません。さっさと暴露すればいいのです。暴露の予告だけを延々とやるのは、ただの脅迫です。
対談でのわたしのもうひとつの主張は、立花さんがすぐに文句があるなら裁判しろというのは、卑怯でしょうというものです。
立花氏は揉めたら裁判で決めるのが一番分かりやすいと何度も主張していて、対談で意見が平行線となったポイントです。
でも、ふつうは裁判なんて、そんなに簡単にしません。
たとえば、ファミレスに入ったら店員にいきなり水をかけられたとします。そこで店長に文句をいったら、文句があるなら民事裁判してくださいと言われたようなもんです。ふつうは話し合いでしょ。とか、まず、謝るべきでしょう。
もし、謝らないで裁判だというのなら、あなたがそれを主張する正義はいったいなんなのか?という質問に立花さんは、結局、はぐらかして答えませんでした。唯一でてきた答えはNHKから国民を守るのが正義というだけです。それと脅迫行為の被害者に謝らないで、裁判しろと開き直ることと、なんの関係があるのでしょう。
さて、とはいうものの私にも大きく反省するところがありました。
多くの視聴者は既得権益者と戦う立花さんという構図に喝采を送っているようです。
立花さんに、あなたは弱者の気持ちがわからない、と決めつけられたことは、自分が既得権益者に視聴者から見えているという事実をつきつけられました。
立花さんに「弱者のためになにをやっているかを具体的に言って見ろ」と挑発されても、ぼくはなにも答えませんでした。
でも、それは答えることができなかったのではなく、それを口に出すことがぼくには重すぎたからです。
立花さんは政治家で、ぼくは経営者です。政治家なら弱者を大切にしろと簡単にいえますが、経営者のぼくにとっては軽々しくいえる言葉ではありません。
なぜなら経営者とは、会社と倒産させずに従業員と家族を食わせることが一番の仕事であって、人間を仕事の能力で待遇に差をつける、ときにはリストラもするというのが仕事だからです。従業員全員を分け隔てなく寄り添うなんて綺麗事をいくらやっても、そのために会社を潰したなら意味が無い。そんな経営者は極悪人です。ぼくは最初に就職した会社が倒産する過程を最後まで立ち会いました。最大500人ぐらいいた従業員の中で社長についていって残った最後のひとりの社員です。そのときに会社を潰すことが経営者の最大の犯罪だと、本当にそう思いました。
経営者が弱者に寄り添うなんてそんな簡単なことではありません。
ぼくがドワンゴを創業したのは、当時、始まったばかりのネットゲームに嵌まった優秀な高校生、でも社会的には落伍者のレッテルが貼られるだろう人が働ける場所をつくろうと思ったからです。
ドワンゴが東証一部に上場したときに部長の半分以上が高卒か中卒、どちらかといえば中卒のほうが多かったことは、ぼくのささやかな誇りです。まあ、続きませんでしたが。
営利企業の経営者である以上、弱者を直接救済することを目的にすることはできないと思っています。ただ、弱者は多くの場合、公平なチャンスすら与えられない。普通の人よりも難易度の高い人生ゲームをさせられています。そういったひとにチャンスを与えるということが、ぼくが経営者として事業を立ち上げるときに、ひそかに目指してきたテーマです。動画サイトも教育事業も。
立花さんは困った人に冷蔵庫を送ったとか聞きました。それは善いことではありますが、一時の助けでありません。そのひとの人生のなにがしかを引き受けたわけではありません。ぼくはこれまでの人生の中で、多くの他人の人生の一部を引き受けてきました。少なくとも立花さんよりも全然多い人数の人生を背負ってきたつもりです。あなたに「弱者のためになにをやったか」なんて問い詰められて答える筋合いはありません。そんなことをおおっぴらに宣伝するつもりはありません。ぼくが人生において黙って行動で示してきたことです。
ただ、そうだとしても、立花さんに指摘された、ぼく自身が既得権益者側の人間にいまなっているというのは、きっとそうなのでしょう。
似つかわしくもない贅沢な暮らしをさせてもらっているぼくが、本当にいまも弱者の気持ちが分かっているのか?
それについては自問したいと思います。立花さんに機会を与えていただいたことには感謝します。
入院生活七変化 その2 安静の大獄
ベッドの上で寝返りすらもできずにじっとしている入院生活というのは、なかなか辛い。景色もほとんど変わらないわけで、病室の窓から見える景色というのが世界の全てみたいな感じになる。
窓の外が明るいか暗いかで大きな違いだから、太陽の出る時刻とかに敏感になる。あー、真夏でも、日の出はどんどん遅くなっていて、昼間の時間は減り始めているんだなあ、とか思ったりする。
そうか、だから、最後の一葉、みたいな小説が生まれたんだなと今更ながらに実感した。
よし、これは最後の一葉ごっこをするしかないと思って、窓の外になんか手頃な木がないかを探してみたが、窓の外はとても見晴らしがよく、季節は盛夏だ。
遠くに見える樹木には鬱蒼と葉っぱが茂っており、とても最後の一葉ごっこができる雰囲気ではない。
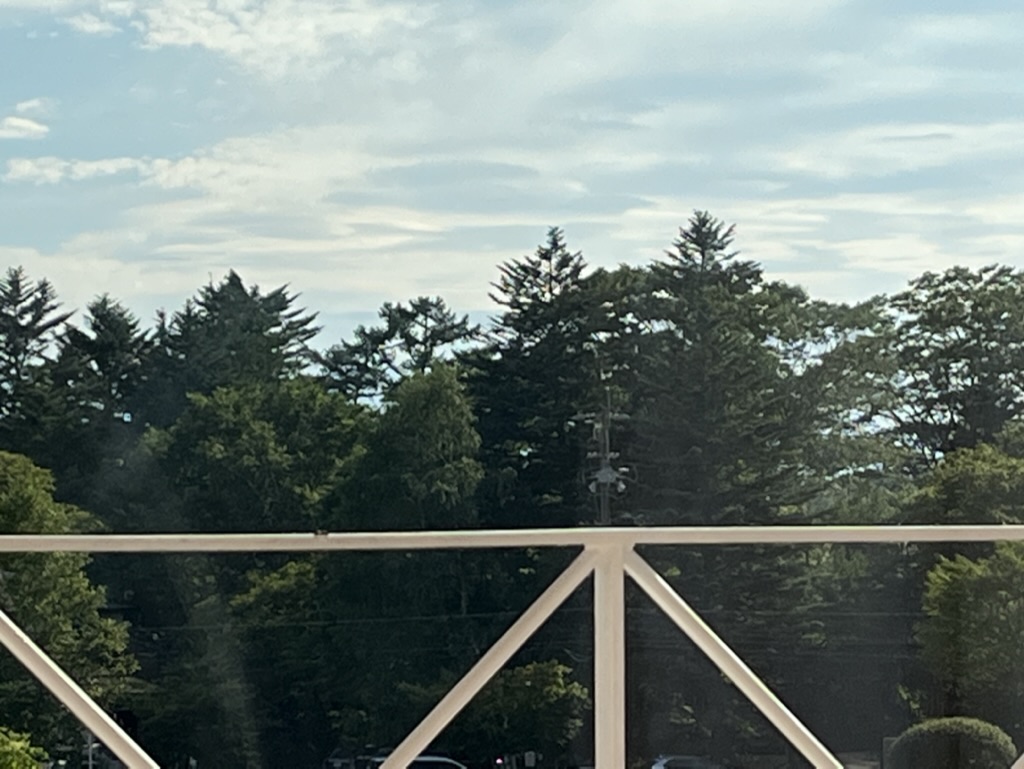
さて、生まれて初めて全身麻酔で手術をしたわけだが、手術そのものは気を失っている間に終わるので問題ない。入院当日の1回目の手術は17分で終わった簡単なもので、体への負担もそれほどない。
全身麻酔による気絶から意識を取り戻して、最初に運ばれるのはリカバリールームだったが、正直、全く疲労感もなくて、やっぱり全身麻酔にしてよかったという感謝の気持ちでいっぱいだった。
ただ、下半身の感覚はない。特に手術した右足は全く感覚がなくてどうなっているか分からないし、知りたくもない。上半身と、左足は一応は動くが、体全体が、非常に重い。頭もぼーっとしていて、よく働かない。痛いとかそういうのはなかったが、じっとしながら何も出来ず、ただ、時間が過ぎていくのを待つというのがとても辛かった。
あー、これは携帯持ってきたけど、誰かとメールとかニュース見るとかそんなことできる感じじゃ全然ないわ。と思った。2回目の手術の時にはAirPodsも持ってきて、ずっと音楽聴いて気を紛らわそう、と固く心に誓った。
辛いのはトイレだ。看護婦さんに手伝ってもらわないとおしっこもできない。一晩ぐらい我慢するかと思ったが、点滴されているせいでおしっこは必ず出るものらしい。
おしっこをするときは電動のリクライニングベッドを動かしてもらって上体を30度ぐらい起こしてから尿瓶にすることになる。あまりに屈辱なので、尿瓶は自分の手で持つことにした。さて、尿瓶におしっこを出すのが意外に難しい。人間は大人になるまでにトイレ以外でそんなはしたないことをしないように心理的に強固なバリアを構築している。
目を瞑って頭の中でトイレにいる想像をしながらがんばっても、夢の中でトイレに行ってもなかなか現実には出ないのと同じように想像の世界で終わってしまう。
しっかりと尿瓶を見つめて、これはおしっこをしてもいい場所だと自己暗示をかけて頑張る必要がある。朝まで30分おきにそんなことを繰り返した。
とにかくよかったのは大きい方がリカバリールームでは出なかったことだ。そんなのを看護婦さんに手伝ってもらうのはちょっと耐え難いし、忍び難い。手術前日はX時以降は食べてはダメと言われているが、その前だったら、たくさん食べても大丈夫だろ、なんてことをしなくてよかったと思った。
そんなこんなでリカバリールームで12時間以上、時々、背中が痛くなるので姿勢を変えるだけで時間を潰した。3時間ごとに体の中で動く部分が増えていく。
じっとしていれば人間の体ってこんな風に回復してくんだなと思った。
病室に移っても、ただ、じっとして患部を冷やしまくって時間が経つのを待つということは変わらない。1日ごとにできることが少しずつ増えていく。
足が腫れないようにするためには心臓よりも高い位置に上げないといけないということだが、最近は別に足をつったりはしないらしく。滑り台みたいなのに足を載せておけばいい。

また、足を上げながら食事もしないといけないから、ベッドに上にテーブルを被せるようにしてリクライニングで上半身を起こして背もたれすることになる。当初はこの姿勢を10分間するのもキツかった。

さて、今回の骨折治療とは、医師の説明を聞いておもったのだが、早く治って退院すればいいというゲームじゃなくて、最終的にどこまでリハビリで元の状態に近づけるというゲームだ。
入院期間とか、早く家に帰りたいとか、大事な仕事をやりたいとか、そういうのは、全部、無視して、いかにリハビリで元の状態に近づけるかを基準に判断しようと、僕は考えた。
いくつか、僕なりの方針を出したのだが、一つは自分の体からのメッセージに従おうということだ。
例えば食事。はっきり言って病院食は美味いわけではない。病気じゃないんだから、何か、美味い弁当を差し入れようという申し出はあったのだが全部断った。なんか、美味いものを食べたいと気がしなかったからだ。病院食は量も少なくて、お腹もぐぅぐぅなったが、それでも残したりした。なぜなら食欲がなかったからだ。空腹感はあっても食欲がないということは、消化じゃなくてダメージ受けた体の回復にエネルギーを使いたいという体からのメッセージだと解釈したからだ。ただ、栄養素は不足したらまずいだろうから、残すのはご飯を中心にすることにして、おかずはできるだけ全部食べるようにした。
それと食欲はないけどチョコは欲しくなったので、チョコの差し入れはしてもらった。これも消化の負担なくカロリーを補充したいという体からのメッセージだと解釈した。
右足動かすときにちょっとでも怖いと反射的に思うような動きはやめる。
また、仕事も無理してやることはしないと決めた。実際、最初の入院して2週間ぐらいは30分パソコンを触ると熱が出るし、疲れて2時間ぐらいは昼寝しないと回復しないみたいな状況だった。そういう時は無理してやらない。多分、足の回復が遅くなると思った。
とにかく安静にして、体がやってもいいということだけやった。
今回、入院して、本でも読んだり、前からやりたかった意識とAIのブログでも書こうかと思っていたんだが、そんな生産的なことはできる余裕もなく、ネットもやらず、ただただ、安静に時が過ぎるの待つ。そんな感じで過ごすことになった。
さて、2週間もほぼ使いものにならなかったのは、もちろん、入院して1週間後に本番の手術をやったからだ。これが本当にきつかった。つまり入院1週間後も入院2週間後も手術から1週間後という意味では変わらなかったからだ。
というところで、今回はおしまい。
入院生活七変化 その1
昨日は何年かぶりにTwitterを再開して新鮮だった。いや、でもTwitterはやっぱりダメだ。無限に時間が吸い取られて、キリがない。
さて、骨折してから、そろそろ1ヶ月になる。手術するのも病院に入院するのも人生初めての経験だ。
僕にとっては、いろいろと興味深い新しい発見があったので、書いてみたい。
まず、なぜ骨折したのかというと庭で滑って転んだからだ。
転んだくらいでなぜ手術が必要なほどの骨折をしたのかと言うと、生後3ヶ月の娘を腕に抱いていたからだ。何がなんでも子供だけはそっと地面に下ろしてから転ぶと、めちゃくちゃ変な角度に足首が捻られて、2回ブチっという激痛が走った。骨折とか人生でしたことないのに、これは折れたなとなんとなく分かった。
いや、思ったけど、これは愛じゃないと思った。そんなこと考える余裕もなかった。勝手に体が動いていた。たんに親とは子供の生命の安全のためには自分の安全など無視するようにつくられている。そういう生き物なんだと思った。
まあ、ここまではいい話なんだけど、結局は転んだわけで足首も折れていたので、僕は体を支えることができず、娘の体の上にほぼ全体重を乗せて落下した。生後3ヶ月の娘の体は柔らかくとてもいいクッションになってくれた。娘は数秒の沈黙の後、当然のごとく大号泣した。
僕は娘をともかく家に連れて帰って安全なところに寝かせようと立ち上がった。激痛はとりあえず無視したが、数歩進んだところで体が動かなくなった。これもあんまり良くなかったんだろうなと、今になって思う。
とりあえず妻の運転するクルマに乗って、近くの病院に駆け込んだ。海の日のある3連休の初日だった。救急で診察してくれた医師は、レントゲンを見るなり、「これは完全にやっちゃっていますね。これは即入院で即手術です。一刻も早くすぐに手術やった方がいい。でも、連休なのでうちでは受け入れできないので、連休明けにまた来てください。」と言われた。
3日後の連休明けに行くと整形外科の医師が診察をしてくれた。「これはすごく腫れちゃっているねー。すぐ入院して手術しないといけないのにほっといちゃったから腫れたんですよ。ダメですよ・・・」医師は僕を叱ろうとして途中で黙り込んだ。連休中なので入院させてくれなかったのは自分の病院だと気がついたのだろう。
ここで教えてもらった豆知識だが、ボルトを入れてくっつけなければいけない骨折の場合は、すぐに手術が必要だ。なぜかというと骨折したら、当たり前だが、骨折した部分がどんどん腫れてくる。腫れると表面の皮膚がパンパンに膨れ上がって伸びてしまう。伸びた部分の皮膚をボルトを入れるために切開手術すると、最後に傷口をきれいに縫い合わせることが皮膚が伸びているのでできなくなる。
だから腫れちゃうまでにとっとと手術をするか、もう腫れている時は一旦腫れが引くまで待たないと切開手術ができないのだそうだ。腫れが引くまでには入院して安静にして患部を冷やしまくって2週間ぐらいかかる。しかもその間に折れた骨が離れた状態で放置されちゃうから、リハビリも時間がかかるのだそうだ。
「手術してリハビリすれば一応は治りますけど、完全に元の状態になるとは思わないでください」突然、医師に宣告された。
「もちろん日常生活には支障ないぐらいには回復はすると思いますが」と医師は続けた。
一瞬、頭が真っ白になった。これってあれじゃん。マンガとかで主人公の最大のライバルとかがよくなる運命じゃん。
お話の中のことだと思っていたのに、まさか、自分がそうなるなんて。
どうやら、いつかはプロのサッカー選手になって活躍したいという僕の子供の頃からの夢は、もちろん、もうほとんど可能性はないことは分かってはいたが、とうとう完全に諦める時が来たようだ。
さて、医師の説明によると普通に腫れが引くまで待つと2週間かかるんだけど、それを1週間に短縮できて、その後のリハビリも回復が早くなるというお勧めな方法があるという。そのためには今日すぐにでも、一回余分に手術が必要だという。
「切開できないんで代わりに骨に穴をあけて鉄の棒を立てて外側で固定するというやり方です」なんか恐ろしいことを言い始めた。より詳しく図解してくれようとしたけど、やりますけど想像したくないので説明しなくていいですと言って断った。
ちなみに結果がこの写真だ。ちなみにこの写真は手術1週間後のもので、それまで僕は自分の足がどうなっているか怖くて見ないようにしていた。

「これ、わりと新しい技術でベトナム戦争のときに使われて広まったんですよ」さすが合理的なアメリカン。ベトナムで骨折した負傷兵は、とりあえずこれで仮に固定しといて輸送して、本国でちゃんとした手術をしたんだそうだ。ベトナム戦争って新しいのか?とも思ったが、整形外科の世界の進歩ってそんなもんなのかもしれない。
次は麻酔医から説明があった。
「今回は全身麻酔は必要ないと思います。背中から麻酔薬を入れる方法にしようと思います」
「いや、全身麻酔の方が気が楽なんですけど」
「まあ、僕も自分だったら全身麻酔にしたいですね」麻酔医は笑ってくれただけだった。いや、だったらしてよ。
でも、結局、全身麻酔になった。やったぜ。
全身麻酔の手術は楽ちんで、麻酔されて意識を失い、目を覚ましていたときには終わっていた。手術後はリカバリールームで一晩を過ごしから、病室へ移動した。僕の右足は全く動かなくて感覚がなくなっていた。いや、関係ない左足も感覚がなかった。ベッドの上で、ずっと右足を固定していて動けない寝たきりの入院生活がそこから始まることになる。
長いので一旦ここで終わり。
本日のNHK党立花党首とのやりとりと立花氏へのメッセージ
本日の午前中に昨晩の立花党首からの公開質問状への回答動画へのコメントを投稿しました。
それに対して、立花党首はツイッター上で公開質問を投稿しました。
川上量生様へ公開質問させて頂きます。
— 立花孝志 NHK党 党首 (@tachibanat) 2022年8月13日
ガーシーの言動が、恐喝というなら、どうして民事や刑事の法的手続きを取らないのでしょうか?
私の質問はこれだけです。
直ちにご回答下さい。
NHK党立花党首の公開質問への回答へのコメントhttps://t.co/LwVH2VWwz3
それ以降かなりのやり取りがあったのですが、いろいろなスレッドに分割されて同時並行で議論が行われたため、私自身も何を議論しているかよく分からない状況になりました。
立花さんも同じ状況だったと推察します。
その後、立花さんが以下のような投稿をされ、直接に会って話すのでなければ、民事訴訟をすると宣言し、一方的にtwitterの議論を終了する宣言を行いました。
ドワンゴ川上さん 直接会って話しましょうよ! それが嫌なら私の方から民事裁判提訴させて頂きます。 https://t.co/FSe779yHnu @YouTubeより
— 立花孝志 NHK党 党首 (@tachibanat) 2022年8月13日
私としてもtwitter上での議論が明らかに混乱していましたので、きちんと立花さんと会話することは望み通りでしたが、議論をきちんと整理するために、会っての対面での会話ではなく、公開書面でのやり取りを提案しましたが、現在まで返答がありません。
立花さんはこれ以上の対話は望まず、法廷で会いましょうということですが、私と立花さんは別に罵倒しあっていたわけではなく、議論を行なっていただけですから、少なくとも民事訴訟をするというのであれば、まず、立花氏が私との議論において、どういう被害を受けていて、それに対して私に抗議をおこない私に反論の機会を与えてから、民事訴訟を提起するのが筋ではないでしょうか?
突然に議論を一方的に中断した上で、会って対談をしなければ、民事訴訟を行うと宣言するのでは、私と議論を続けることが、立花氏にとって都合が悪いので逃げようとしているようにしか思えません。
上記の民事訴訟宣言と同時に投稿されている動画によると立花氏が問題視しているのは2点です。
・ ガーシーが「違法行為」をしていると断定をし、その前提に立って発言をしている。
・ 立花氏の「後ろめたくなければ恐喝にならない」、という主張が「総会屋と変わらないものである」という私の評価に対して、「総会屋」というワードを使ったこと。
そして、民事裁判としては、債務不存在の訴訟を検討しているとのことです。私の発言の「違法行為」と「総会屋」というワードが問題だというのであれば債務不存在ではなく、名誉毀損ではないかと思います。なぜ、どういう理由で訴訟するのかが決まってないのでしょう?
まず民事訴訟をすることがありきで、どういう理由で訴訟ができるかを今から探すということであれば、まさに民事訴訟の目的は、私の言論封殺ではないでしょうか?
債務不存在で訴訟をするということですが、私は最初の公開質問状の最初の質問にあるように、立花党首にガーシーの行為についてNHK党首としての立場と見解をはっきりとお答えくださいと意見をしているに過ぎません。別にガーシーの行為によって私が受けた損害を立花さんに補填するように要求しているわけでもありませんし、立花さんにガーシーの行為に責任があるというのも私の意見であって、立花さんにそのことを強制するものではありません。私はむしろ立花さんが堂々と、自分とガーシーは一心同体であって、ガーシーのやってることは、一切悪いと思っていないし全力でサポートすると、例えば主張されるんだとしたら、なんて立派な返答だと思って引き下がるでしょう。
さて、私は実際のところ立花さんが、まさか言論封殺のために民事訴訟をされるとは思っていません。せっかく「違法行為」と「総会屋」というワードが問題だとご指摘いただきました。この二つのワードはちょうど私がNHK党と立花党首が行なっている行為に対して私が批判したい核心の部分であり、誹謗中傷を目的としていません。あらためて私がなぜ「違法行為」と「総会屋」というワードを用いたのかを説明します。私が求めるのは議論であり、反論です。もし、無視をするという選択をされるのであれば、それももちろん立花党首の自由です。
ガーシーの行動が恐喝にあたるかどうかを決めるのは刑事裁判だというのは、立花さんが言われるまでもなく当然でしょう。しかし、私は裁判官でも弁護士でもない一般市民ではありますが、私なりに具体的な根拠を示した上で、ガーシーの行なっていることは「恐喝」であり違法行為だと主張しています。私の発言が間違いであるなら、立花さんも具体的な根拠をもとにそうじゃないと主張されればいい話じゃないですか?私が間違っているのであれば、立花さんの言葉を借りれば、何も恐れる必要はないはずです。ガーシーの行動が違法行為かどうかを議論するのがそんなに嫌なのでしょうか?なぜ、堂々と、ガーシーの行動はこういう理由で違法行為ではないと主張されないのでしょうか?
ガーシーの行動が違法行為でない理由について、立花さんは明確に答えていません。昨日の公開質問状の回答動画では、ネタを懸賞金で募集したとしても、もし、川上、ドワンゴ、KADOKAWAに後ろめたいことがなければ何も起こらないのだから恐喝にならないという主張をされていました。本日の民事訴訟を宣言する動画では、弁護士からのメールをチラッと見せただけであり、そもそも弁護士にどういう質問をした上での回答なのかも分からず、私の主張とどこに相違点があるのか、明確には示されていません。
ガーシーの行動が違法行為と考えるかそうじゃないかは、私と立花氏との議論において根本部分の重要なところですから、ここに関してだけはきちんと文章で示されるべきではないでしょうか?
そうできないのあれば、ガーシーの行動が違法行為かどうかについて議論をすることが余程、立花さんにとって都合が悪いと考えるほかありません。
FC2髙橋さんも懸賞金を提示してネタを集めることは違法ではないというようなことを主張されていますが、懸賞金をつけてネタを集めること自体が問題と言っているわけではなく、1億円の賠償金免除を要求した後、交渉が決裂したことを理由にネタを集めて暴露すると公開の場において宣言したことをもって恐喝だと私は主張しています。
そのあたり立花さんの違法じゃないという主張は、ガーシーが和解しなかった報復の攻撃であることを明確に発言していることを故意に無視しているように思えます。
立花さんが考えるガーシーの行為が違法じゃないという、ちゃんとした理由を示していただけないでしょうか?
なお、立花氏は議論が平行線なんだから訴訟で決着をつけるべきだと再三主張しています。しかしながら立花氏はそもそも違法じゃないという根拠をちゃんと示していません。
そしてガーシーはドバイに逃亡しているわけですから、刑事裁判で決着をつける見通しは全く立っていません。裁判で恐喝と認定されない限り責任は取らないという立花氏の姿勢は、ガーシーが、もし本当に違法行為をやっていたのだとしたら、その被害を野放しにして、実質的に違法行為を幇助する行為ではないでしょうか?ですから、裁判以前にガーシーの行動が違法かどうかをきちんと議論することは必要であるし、意味のあることだと思います。
最後にNHK党で立花さんがガーシーを使って目指されていることと総会屋の類似性について指摘させてください。
立花さんはガーシーさんの暴露について、悪が暴かれることは正義であり良いことであると主張されているように思います。しかしながら、過去において総会屋も同じく悪を暴いてきました。しかし、金銭的要求などの言うことを聞く会社の悪は暴かずに、言うことを聞かない会社の悪を暴くと言うのが、総会屋のビジネスモデルです。そして実際に総会屋が悪を掴んでなくても、何かターゲットにされたら怖いと思って、多くの企業が総会屋と付き合って、お金を支払っていました。
何も後ろめたいことがなければ堂々としてたらいいじゃないですかという、立花党首の言い草は、まさにかっての総会屋も使っていただろう理屈ではないでしょうか?
総会屋は自分もターゲットになるかもしれないという恐怖で企業をコントロールしてきました。ガーシーさんの手法とも一致します。ガーシーさんがご自分の影響力で実質的な金銭的要求をしているという事実は、私以外にあるかどうかは知りませんが、現にガーシーはXXが自分の仲間になった、謝ってきたと言うことを吹聴しており、少なくともガーシーの影響力による恐怖に影響されていると思える人物はたくさんいます。
また、ガーシーはネタを出すことを、再三、予告して、相手に屈服を要求しています。悪を暴くのに散々予告をする理由はなんでしょうか?相手に暴露されたくなければなんらかの交渉をしてくるように圧力をかけているのではないでしょうか?まあ、実際に連絡してくるようにガーシーさんは毎回発言されていますよね?
おそらくサロンがオープンして最初の暴露は、言うことを聞かない人たちを中心とした見せしめのための暴露ではないでしょうか?おそらくは世の中へのアピールのために政治家も何名か狙うのかもしれません。その後は総会屋と同じ手法で影響力を拡大していき、ビジネスに変えていくのではないかと懸念しています。
少なくとも現在のガーシーの影響力がこのまま維持されるのであれば、そういったことは”可能”であると考えます。
立花氏のガーシーを擁護する発言やガーシーが違法であると裁判で確定しない限りは違法とは認めないという姿勢は、ガーシーが総会屋と似た権力を持つことを手助けしているように思えると言うのが私の意見です。
以上について、立花さんの見解をそれなりに回答いただけるのであれば、直接、お会いしての話し合いを受けようと思います。ただし、現在、私は入院中であり、退院後9月以降の日程となることをご了承ください。
あ、別に民事裁判が怖いわけではないので、直接、お会いしようがしまいが、勝手に訴訟やっていただいても構いません。並行でやればいいだけの話です。
以上
NHK党立花党首の公開質問への回答へのコメント
昨日の公開質問状に対して、早速、立花党首から動画にして回答がありましたので、その内容についてコメントします。
回答動画は約36分間ありますが、重複や繰り返し、また、質問とは関係ない内容も多いので重要なポイントを抜き出すと以下の4点だと思います。
・ 立花党首は、ガーシー(東谷議員)が違法な恐喝をしているという認識はない。(6:20〜)
・ 50万円から300万円の懸賞金をつけてネタを募集する(そして暴露すると宣言すること)については、もし、川上、ドワンゴ、KADOKAWAに後ろめたいことがなければ何も起こらないのだから恐喝にならないというのが立花党首個人としての見解。(8:28〜9:35)
・ 立花党首は国会議員であるガーシーの上司であり監督責任があることを認めた。(30:09〜)
・ もしガーシーが違法行為をしていたのなら、謝罪をするなり党首を辞任するなり責任を取る(30:15〜)
この4点を中心にコメントをします。
まず、公開質問状でも指摘させていただいたように、客観的に恐喝としか思えない行動を、FC2高橋氏と東谷議員は共同で行っています。これは事実として指摘させていただきました。
まず、東谷氏と高橋氏の行動はほとんどネット上の公開の場で行っています。唯一、第3者からわからない部分があるとすれば、私とガーシー、あるいは私と高橋氏との間でのやりとりでしょう。私とガーシーとのやりとりは既にガーシーさんがネットに公開されています。また、核心である私と高橋氏とのやりとりについては、昨日、高橋氏が公開した動画で、警察に逮捕されないようにしてほしいといったこと、賠償金1億円について取り下げてほしいと言ったことは事実であること。しかもそのような条件を提示した理由は、私がガーシーさんを恐れて和解したがってると誤解していたためであり、1億円ぐらいKADOKAWAにとって大した金額ではないと思ったからだということまで告白しています。
さて、高橋氏との和解交渉の決裂の後、和解しなかったので、ドワンゴとKADOKAWAを攻撃する。和解しなかったことを後悔させてやる。ドワンゴ、KADOKAWAのネタを最大300万円高橋氏がスポンサーになるので募集する、とガーシーが発言したのはネットの公開の場で行ったファクトです。もし疑問であれば、東谷議員に一言質問をすれば確認できるはずです。
どうみても明白な脅迫ではないでしょうか?
いうまでもありませんが、何か具体的な事実を暴露すると言って、金銭的な要求をするのは、具体的な事実が後ろめたいことであり真実であったとしても恐喝です。
そして具体的な事実が指定されてなくても、例えば「俺はお前の知られたくないことを知っている。暴露されたくないなら金をよこせ」というのも恐喝していることには変わりません。
立花党首の「後ろめたくないことがないのであれば恐喝ではない」という主張は、まったく、よく分からない詭弁でしかありません。これは昔、よく総会屋が主張していた理屈ですよね?後ろめたいことを暴くのは社会正義だのような主張も含めて立花党首は、ネットで活動する新しい総会屋のようなものを合法的なものとして国民に認めてもらいたいと主張されているように思えます。
さて、立花党首は回答動画において、自身のガーシーこと東谷議員への監督責任を認めました。また、恐喝が事実であれば、責任を取ることも明言されています。
しかしながら上記のように、客観的にも恐喝と十分に思える行動を東谷議員が行ったことは明白です。そして立花党首は自身で認められたように監督責任がある当事者であって、無関係の第3者ではありません。
もし、上記に示した事実にも関わらず、東谷議員が恐喝をおこなっていないというのであれば、そう考える根拠を示してください。もし、それが今回主張された後ろめたいことがないのでなければ恐喝にならないという珍解釈を維持されるのであれば、それでも結構です。改めて監督責任のある当事者として明言してください。
なお、回答動画の中では、まるで他人事のように、再三、民事訴訟をするべきだと主張していますが恐喝は犯罪であり、刑事事件でしょう。立花党首は監督責任も認め、もし、違法行為があれば責任を取ると明言された当事者です。明白な事実を突きつけられても、裁判をしろと開き直るのは無責任な態度であるとともに、東谷議員と一緒にNHK党として組織的に違法行為をやっているとも思われかねない行動ではないでしょうか?
いずれにせよ、私は立花さんに法律相談のつもりで公開質問状を送ったわけではありません。東谷議員の行いへの立花党首の責任を問うたものであることを改めてご理解ください。
NHK党 立花孝志党首への公開質問状
立花孝志 様
はじめてご連絡をさせていただきます。株式会社ドワンゴで顧問をやっている川上量生ですが、今回は個人として質問状をお送りさせていただいています。
早速ですが、貴党の東谷義和議員(通称ガーシー)が、7/31の”『死なばもろとも』ガーシー 出版記念 ガーシー×箕輪厚介”というYoutube番組において、自分の親友であるFC2の創業者の高橋理洋氏を嵌めたドワンゴを許さないとしてドワンゴとKADOKAWAを攻撃するという発言を行いました。また、「分けわからん変な裁判で金とろうとしやがって」とドワンゴに連絡してこいという発言を行いました。
私はたまたま番組を見ていましたので驚いて、人を介して、東谷議員に連絡を取ったところ、高橋理洋氏と話してほしい。できれば和解してほしいと言われました。
その後に高橋理洋氏とLINEで電話をしたところ、高橋氏が私に希望されている条件は二つありました。
一、警察に働きかけて、高橋理洋氏が日本に帰国しても逮捕されないようにしてほしい。
一、先日、ドワンゴとFC2の特許訴訟について、知財高裁で判決が出てドワンゴが勝訴し、FC2が1億円の損害賠償をドワンゴに支払う命令がでた件につき、訴訟を取り下げるか、差押をしないでほしい(要するに1億円を支払わないことに合意してほしい)。
2点とも非現実的な要求であり、そもそも私の持っている権限でも不可能であると言うことを高橋氏には説明しましたが、髙橋氏は何の譲歩もしないのかと立腹されました。
その後、8/3のインスタライブで東谷義和議員は、髙橋氏とドワンゴとの交渉が決裂したので攻撃をすると発言し、視聴者にドワンゴとKADOKAWAのネタを募集することを告知しました。また、ネタの提供者にはFC2高橋氏から50万円から300万円の謝礼を払うことも同時に発表しました。
また、翌日の8/4には髙橋氏は「ドワンゴに静かに宣戦布告しました。」とツイートをしました。
既に判決の出ている1億円の賠償命令に対して、放棄しなければ攻撃をするというのは、ただの恐喝です。それを国会議員がネット上で堂々と公言するというのは、非道であるというばかりでなく、これが現実に起こっていることが信じられない理解に苦しむ出来事です。
これらの大まかな部分については、私が8/7に書いたブログ記事において既に書きました。
これはネットでも大きな話題になりましたが、立花党首は現在までこの件については、一切、コメントをされていないと認識してます。
しかし、東谷議員の発言については変化が見られ、川上の相手は高橋氏であり、自分はKADOKAWAを攻撃すると一歩距離を置き、役割分担をするかのような発言をするようになりました。また、私が西村博之氏を使って攻撃していると、あたかも自分が攻撃されている側であるかのような発言を繰り返すようになりました。
しかしながら、東谷議員と髙橋氏は、今後、ガーシーがさまざまな人の暴露を行うと宣言しているサロンを共同運営するパートナーであり、事実上、東谷議員と髙橋氏が一体となって、私と私の会社を恫喝しているという状況に、現在も何ら変わりはありません。
上記のことは、ほぼ全てについてログなどで確認が可能な現在進行形の事実です。また、そもそも多くは東谷議員と高橋氏がネット上で公言していることであり、現在も検索すれば見つかります。
以上の事実を踏まえて、東谷義和議員が所属するNHK党の党首である立花孝志さんに質問をします。
一、上記の東谷義和議員の行動について、NHK党首としての立場と見解をはっきりとお答えください。
一、東谷義和議員は違法な恐喝に思える行動を公然とおこなっていますが、被害を訴えようにも海外にいることと国会議員という高い社会的立場にあり、不逮捕特権などもあることから、たとえ(不逮捕特権のある)国会の会期中でなかったとしても司法による救済が本当に可能かどうかも疑わしいと考えています。不逮捕特権は国会議員の自由な活動のために保障された権利であるということですが、国会議員の自由な活動に脅迫や恐喝を公然と行なうことが含まれているとは考えられません。NHK党としては国会議員の持つ非常に高い社会的地位の濫用につながるような行為を所属の国会議員に対しては戒める責任があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか?
一、立花さんは、これまでNHKの受信料問題において、素人に分かりにくい法の不備を指摘されたりで活躍されています。また、今回の参議院選挙においても、ビジネスとして政党助成金の制度が成り立つということを発見され、しかもちゃんとその事実を公表した上で選挙戦を戦いぬき結果を出されました。立花さんの法制度と運用についての深い理解を示す事実だと考えます。
今回の東谷議員が海外から国会議員の立場で情報発信をすると違法な行為であっても処罰されにくいということも、分かっていて立花さんは利用されているのでしょうか?現に、東谷氏がドバイから活動できるように立花さんはさまざまな支援を行なっておられます。立花さんの見解をお聞かせください。
以上
※ 期間限定でtwitterアカウントを公開します。gweoipfsd@gweoipfsd。これが唯一の川上本人のtwitterアカウントになります。
AIビジネスの本命(と僕が考えていること)
最近、内容はともかくとしてブログを久しぶりに連続更新した。実は足を骨折して3週間前から入院していて暇だ。とは言ってもベッドの上で起き上がってパソコンで作業するのが苦にならなくなったのは、やっと今週からだ。そして、昨日、抜糸も終わって、3週間ぶりに寝返りとかしてみたりして、いい感じだ。
というわけで、5年前ぐらいから、考えていることを少し書いてみようと思う。ディープラーニング革命以降、AIって新しい産業になるのかという質問される機会が多いので、僕も何回か考えてみたのだが、結論を言うと、ちょっと大きなビジネスはできそうもないよね、と言うことになった。が、一つだけこれはいけそうじゃないかというアイデアがあって、僕はいいアイデアを秘密にする価値はないと思っているので、5年前からいろんな人に喋ったし、有識者会議でもちょっと披露したりしたのだが、あんまりみんなピンと来てくれない。
いいアイデアだと思うんだけどなあ。そんなに技術的には難しくないから、つまらないテーマに思われているのかもしれない。でも、ビジネスになるのはそういうやつだ。5年前に考えたことなので、忘れかけている部分もあるが、思い出しながら書いてみる。
まあ、ざっくりいうと業務管理システムと人事システムと給与システムをつなげたようなものを作るということだ。ポイントは給与の上げ下げやボーナスは年に1回とか2回しかないことが多いが、それをAIを使って高頻度に仕事を評価し、給与をちょっと上げたり下げたり、マイクロボーナスを支給したりすることができるというのが核となるコンセプトだ。
これだけではちょっと分からないかもしれないのでと、まずはそもそもAIをビジネスにするのがなぜ難しいかを考えてみる。
簡単にいうとサービスのパッケージングが難しいからだ。ビジネスとして大きく成長させるためには、何からのスケーリングする仕組みが必要で、そのためにはAIという技術を何らかの形で再利用できるパケージにしなければならない。
これが、AIの場合は難しい。AIは、非常に汎用性の高い技術なんだけど、どうやってなんのために使うのかという自由度が高すぎて、ちょうどいい感じに再利用するようなパッケージングを見つけにくい。いろんな異なる目的が与えられて、エンジニアがその都度、頑張る、みたいなことを繰り返していても、労働集約的なビジネスにしかならなくて、なかなか大きなビジネスになりにくい。
似たような例を考えると、例えば「数学」というテクノロジーを使ったベンチャービジネスで大成功しようということで、めちゃくちゃ優秀な数学者10人が手元に集まったとする。ぶっちゃけ、だからといってどうしようもできなくて途方に暮れることだろう。
そして多くのビジネスにおいて、AIは必要とされるパーツのほんの一要素でしかない。AIじゃない部分のパーツの方がビジネスに成功において重要な場合がほとんどだから、AIだけで新しいベンチャーを作るなんていうのもちょっと現実的じゃなかったりする。例えばアクションゲームで敵兵の動きがとても優秀なAIがコントロールします。とか言ったって、ゲームが面白いかどうか、大ヒットするかどうかにはどれだけ影響あるか微妙だ。
業務システムにAIを組み込んでも似たようなことで、AI機能で勝負して、各企業がこぞって導入する業務システムなんて想像することは非常に難しい。何の効果があるのか具体的にはっきりしないと企業は簡単に新しいシステムを導入してくれない。
まあ、何だけど上記の人事・給与をつなげた報酬マネジメントシステムなら、各企業がこぞって導入するようなものになり、ビジネスをスケールできる可能性がある。
なぜかというと高頻度なマイクロ報酬マネジメントシステムを作ることによって、業務が効率化し、社員のモチベーションも上がり、結果として明確に人件費節減を実現できる可能性があるからだ。AIとかさっぱり分からない経営者も人件費の節減に繋がるなら、前向きになる。
ビッグマザー
この魔法のような報酬マネジメントシステムに仮の名前をつけよう。この記事では「ビッグマザー」というシステムだということにしよう。
ビッグマザーの原理は簡単だ。ビッグマザーには二つの重要なインタフェースが存在し、一つは、従業員の勤務状況をを判断するトリガーになるイベントを収集するBMEIと、従業員への報酬を与えるBMRIだ。
基本的にはBMEIからの情報をもとにBMRIのパラメータを調整して、従業員のコストパフォーマンスを最大にするという問題を解くだけだ。
重要なのは企業により、また、職種により、仕事のアウトプットを判断するデータは異なるし、人事制度に許される自由度が異なるだろうから、BMEIとBMRIにつなげるモデュールは変えたりカスタマイズしなければいけないという点だ。
ここにノウハウが貯められる余地がある。そしてノウハウの再利用のためにBMEIとBMRIの仕様が一つに統一さなれているとみんなハッピーであり、ここにデファクトをとれる大きなチャンスが存在する。
ビジネスの形態としては、オラクルとかがモデルになる。基本、コアモデュールとオプションモデュールを販売する会社にして、カスタマイズはVAR業者に任せるみたいなモデルが考えられるだろう。
大まかに説明すると、こんな感じだ。
ゲームの参加プレイヤーのイメージ
次にこのビジネスに可能性があるとして、どういうプレイヤーがありうるかを考えてみよう。
ここが本気でやったら決まりだよね、というのはSAPとSalesforceあたりか。まあ、でも巨大プレイヤーは小回りがきかないと相場が決まっている。
国内で考えると、企業の総務部とか業務部とかにシステムを納入できている会社は有資格者だろう。大手SIベンダーとかポジションは良さそうだが、そんな器用なことは出来なさそうだから、freeeみたいなところが良さげかもしれない。
あと、これビッグマザーのちゃんとした稼働実績を最初に作るのが超大事だから、ある程度均質な職種で実験できる社員やバイトをたくさん持っているようなところがいいかもしれない。ITリテラシーも高そうなところで言うと、デジタルハーツとか。
まあ、会社名は読者がイメージしやすいように適当に選んだだけだ。
成功するために必要な人材。
当然、B2BなのでB2Bに必要で強力な営業体制だったり、AIエンジニアのチームも必要だが、最も重要なポイントはビッグマザーの設計をするアーキテクトだ。技術にも企業の人事や労務にもビジネスにも習熟している人が望ましいが、まあ、いないと思うので、技術と地頭優先であとは覚えてもらうと言うのが現実的か。データアナリストみたいな人は向いてない。数字に強くて地頭がいい人がいい。若い森岡毅氏みたいな人をコンサル辺りから探してくる感じじゃないか。
ちゃんと動くビッグマザーを作ってちゃんと効果があるという実績をいかに短期間にたくさん作れるかが成功のキーファクターになる。
本当に人件費が抑制できるか?
多分、できるんじゃないかと言うのが、僕の勘だが、まあ、でも5年前と違って、ビッグマザーみたいなシステムは既に世の中に出現しつつある。
UBER EATSとかだ。この配達員に配られているアプリはゲームみたいな感覚で配達員のモチベーションを上げて働かせようという仕組みが組み込まれている。
まあ、きっと効果はあるんやないかと思う。
どれぐらいの投資が必要か?
僕の丼勘定によると、プロトタイプを作って本稼働させて最初の実績を作るまで3年で20億円ぐらい?
それからある程度成功するための勝負には50億円〜100億円ぐらい?それぐらいはかかるように思う。
そのあとは競合の有無とかによって全然変わるよねー。
ビッグマザーのアルゴリズムはどんなイメージになる?
どういう報酬の与え方がいいかは機械学習で決めるのだとしても、結果はある程度は想像できる。おそらく、時給のようにあげると下げるのが難しいし、上がったことをすぐに従業員が忘れてしまうようなものへの配分はできるだけ減らすように学習するんじゃないかと思う。もっと短期的なモチベーションを上げるような一過性の報酬を短い間隔で渡すと言うことになるんじゃないか。
そうすると人件費の向上も最低限に抑えられて、モチベーションも上がるようなバランスを見つけることができるように思える。しかもモチベーションが上がったあとは、きっと微妙にパラメータを変えて、モチベーションを下げずに平均報酬を下げるようなこともできるんだろうな。つか、UBER EATSとか絶対やってそう。
・・・・・。
つうか、これ、なんか最悪のシステムだな。こんなのが成功したら世の中悪くなるじゃん。法律で規制した方がいい。
このビジネス、さっきは思いつかなかったけどパソナみたいな会社も向いているかもしれない。
なんか、思い出してきた。5年前も同じ結論になって、それ以上考えるのをやめたんだった。忘れてた。
まあ、いいや。でも、まあ、多分、こういうシステムもビジネスも、遠くない将来に生まれると僕は思う。その時、外資に持ってかれるよりは、誰であれ日本のプレイヤーがいた方がいいんじゃないか。
と言うことで、こんなAIビジネスいかがでしょうか?
僕自身も、もし拉致監禁されてAIでベンチャー作れと脅迫されるようなことがあれば、真っ先に自分でもやりたいと思うビジネスだ。
以上